開発はチャレンジの連続
「苦労」と「面白さ」とは表裏一体です

開発の苦労と面白さ
Page.2
1000分の2秒で全てを処理する

有料道路の電子料金収受システムであるETCもまた、時代を変える新しいシステムとして登場した。2001年から一般利用が開始され、現在では道路輸送に欠かせない社会インフラとして定着している。
そしてサンリツは、このETC開発に最初から携わってきた。
第1世代ETCのソフトウェア開発を担当したシステム開発部長の三堀 学が当時の状況を語る。
「ETCの運用が開始するまでには、5~6年の前段階がありました。当時、道路の電子料金収受システムは世界的に研究開発されていて、1994、95年にはシンガポールで、市街地へ乗り入れるクルマに課金するシステムのコンペが行われました。サンリツも他社とJV(共同企業体)を組んで参加しました。結果的には負けましたけど、コンペのために、車両の検出、ゲートと車両の通信、アプリといった要素技術の開発を事前に行いました」
その後、97年に当時の建設省(現・国土交通省)、日本道路公団(現・東/中/西日本高速道路株式会社)が中心となり、小田原厚木道路と東京湾アクアラインで電子料金収受の試験を開始。翌98年にはETCの仕様書が開示され、全国導入に向けたシステム開発がスケジュール化された。
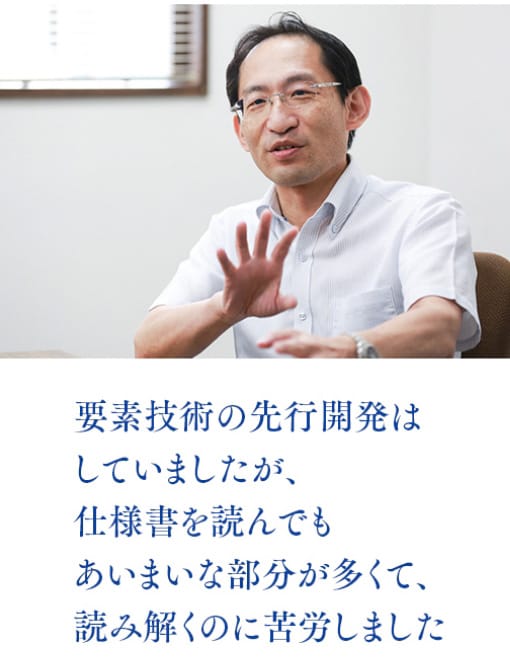
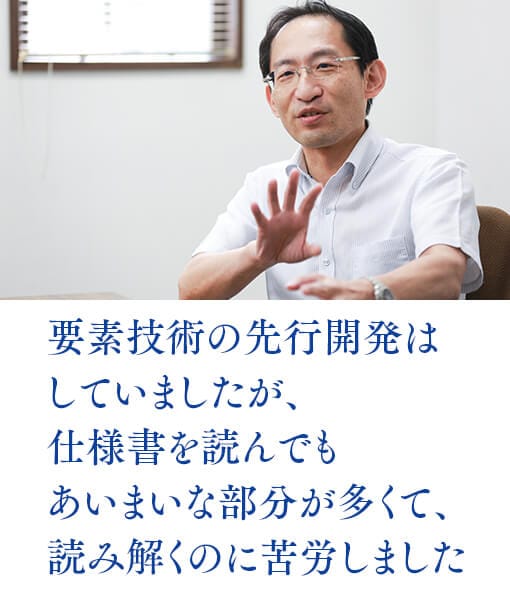
開発に手を挙げるJVがいくつもでき、サンリツはその中の1つに参加。クルマの形状を測り、料金を計算して課金するというコンピュータ処理の部分を担当することになった。
日本道路公団への入札の結果、参加するJVは東名高速道路と伊勢自動車道の一部区間のシステムを受注。99年から納入に向けた具体的な製品開発が始まった。
しかし、ETCは全く新しいシステムだ。
発注側にとっても、受注側にとっても未経験のジャンルだけに、開発のスタート時は、全くの手探り状態だったと先進計測制御(AMC)事業担当取締役の高倉広義は振り返る。
「それまでに要素技術の先行開発はしていましたが、製品化のための仕様書を読んでも、あいまいな部分が多くて、具体的な要求やゴールがよく分からない。道路の仕事に慣れている企業なら、ある程度の勘所はつかめたのかもしれませんが、読み解くのに苦労しました。
さらに、開発が始まってから、インターチェンジによって、ETC設備の取付位置やスペックが違う、同じインターチェンジでもレーンによって使い方が違ったりと、仕様がバラバラなことが判明しました。いくつもの仕様をクリアするのが最初の壁でしたね」
前例のない新しいプロジェクトで、決まっていないこと、分からないことだらけ。少しずつ目標を明確化したうえで、精力的に開発を進めていったが、それでも仕事量は膨大になった。結果的に無駄になった仕事もかなりあったと、SE・ソフト開発部門担当常務の上之原尊は言う。
「結局、システムを2回半くらい作りました。全体像や細かな仕様が必ずしも明確にならないまま作りましたから、最初の1回分は、使い物にならず捨てました。混沌とした状態の中、手探りで進めていったのは他のJVも同じで、やはり作り直したメーカーがいくつもあったと聞いています」
システム全体を構成する要素の多さも、開発のハードルを上げていた。
例えば、クルマ側の車載器もそのひとつ。
「車載器も仕様書に従って数多くのメーカーが手掛けました。しかし、仕様書はそこまで厳密には書かれていないので、開発過程の解釈によってどうしても製品に違いが生じる。通信の手順が微妙に異なり、条件によってはゲート側とうまく通信できるもの、できないものが出てきます。
でも、車載器は後からは修正がきかない。結局、ゲート側のシステムで、車載器の違いを全て吸収できるようにしなければなりません。同じような問題が次々に湧いてきました」(三堀)
こうした目の前の手当てに追われる一方、開発競争の核心はDSRC通信(狭域通信=Dedicated Short Range Communication)に絞られていた。
「2ミリセコンド(1000分の2秒)の間に、車種・入口・出口の情報から料金を計算し、100万件のクレジットカード情報と照合し、課金するという処理をしなければなりません。そこがETCシステム最大のポイントで、各社とも独自の技術を使い、それぞれにDSRC通信を作り込んでいきました」(上之原)
2000年当時、これだけの処理ができる性能のコンピュータを、寒暖差や風雨、振動、排気ガス、等々にさらされる道路際で24時間稼働させるのは、大変なハードルの高さだった。
技術的な難しさゆえに、各JVに参加している電機メーカーは超大手の企業ばかり。同じフィールド、同じ条件で、サンリツが大手メーカーと対等に競う初めての経験となった。
大手メーカーと対等に競う
開発競争の結果は、ほどなく明らかになった。
日本道路公団が、各JVが作ったシステムを集め、試験する機会があったからだ。2週間かけて、さまざまな状況を想定した評価が行われた。参加したのはサンリツを含めて7社。サンリツ以外は、全て大手メーカーだった。
この試験に合格した製品から、次のステップに進むことができる。実際の高速道路に設置して、パイロット試験が行われるのだ。もちろん、評価試験で改善点が指摘されれば、持ち帰って修正することになる。
システム評価の採点表は公表されてはいないものの、結果、サンリツは7社のうちで、1番にパイロット試験のステップに進むことが決まった。しかも、試験結果が出た翌週には、東名高速道路の一部と伊勢自動車道にテスト設置というスピードぶりだ。
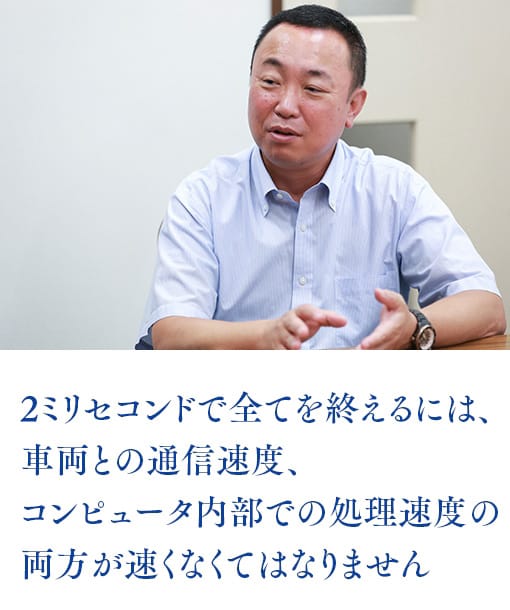
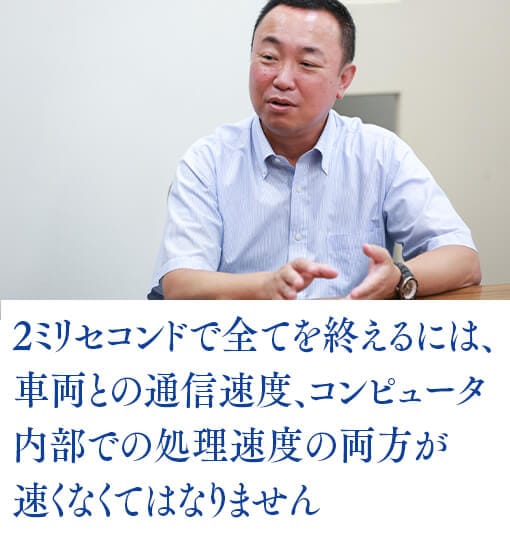
サンリツのシステムの特徴は、コンパクトなサイズながら、高速な処理ができることにある。
「最初からコンパクトな製品を目指して、2チャンネルを1スロットサイズに収めました。他社は2スロット以上のサイズですので、実装密度で4倍以上ということになります。CPUの開発から手掛けていたため、熱対策を講じながら、ファームウェア用、マルチタスクOS用に、別々のCPUを高密度に実装することができました。コンパクトなのでコストや設置場所でも有利です」(高倉)
もちろん、処理速度にもさまざまな工夫が凝らされた。
「2ミリセコンドで全てを終えるには、車両との通信速度、コンピュータ内部での処理速度の両方が速くなくてはなりません。それぞれの割り当て時間が決まってくるので、車両との通信は、ハードとソフトのブラッシュアップを重ねてスピードを上げていきました。コンピュータの内部処理は、例えばクレジットカードの照合を順番にやっていたら間に合わないので、特別なアルゴリズムを開発して、時間内に収めました」(三堀)
各所に技術的な工夫はあったものの、大手メーカーをしのぐ製品を作れたのは、サンリツの社内体制や仕事スタイルに負うところが大きいと上之原は言う。
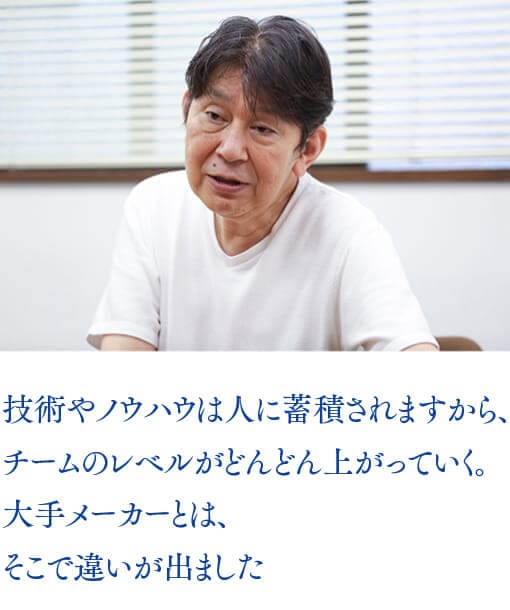
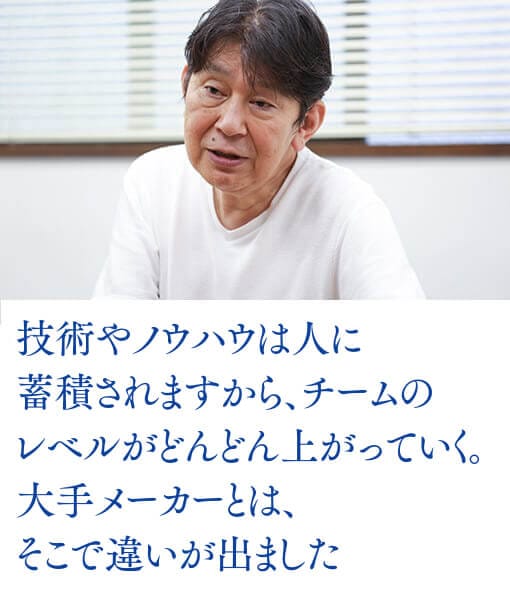
「シンガポールのコンペに出た時から、ハードとソフトのエンジニアが一体となってチームを組み、ほとんど同じメンバーで開発を進めてきました。技術やノウハウは人に蓄積されていきますから、チームとしてどんどんレベルが上がっていくし、必要な技術は全て内部でまかなえる。組織の縦割りや垂直分業が当たり前で、技術者の異動も多い大手メーカーとは、そこで違いが出たのではないでしょうか」
現場でのパイロット試験が始まってからも、新しいシステムゆえの“想定外”はいくつも現れた。
例えば、緊急車両の取り扱いについて、最初の仕様書では想定されておらず、実際に緊急車両がやってきて問題が発覚。さかのぼって仕様書に項目を追加してもらった上で、システムを修正するといったひとコマもあった。
そんな数えきれないほどのハードルを、サンリツはもちろん、プロジェクトに参加した全てのエンジニアが1つ1つ乗り越え、ETCは計画通りに2001年から一般利用を開始した。高速道路キャッシュレス時代の幕開けだった。
利用開始当初、サンリツが担当したシステムは、東名高速道路と伊勢自動車道の130レーンに設置された。その後のETCの普及に伴い、レーン数もエリアも拡大。現在では、はるかに数多くの料金ゲートでサンリツの製品が、24時間365日、膨大な数の通行車両と1000分の2秒の通信を交わしている。
開発の苦労と面白さ Index
Page.2




